
精神分析的な臨床実践には,知的な学習と,体験的な学習が必要だと言われています。
精神分析研究会・神戸では,知的学習として,幅広い理論や技法に触れるための系統講義,重要論文を精読する文献講読という2つのプログラムを用意しています。
体験的学習としては,事例の検討が中心となります。多様な事例に触れることのできるセミナーの事例検討と,少人数でのグループスーパービジョンがあります。
2026年度講義テーマと内容
大阪教育大学保健センター
府中みくまり病院
講義テーマ「シュレーバー – 精神病水準の理解」
今回はフロイトの症例の中の唯一の精神病であるシュレーバーを取り上げ、これまで了解不能と考えられた精神病に対して、その病態と症状形成についてフロイトがどのような形で精神分析的な視点から理解を試みたのかを振り返ります。
【参考文献】1)自伝的に記述されたパラノイアの一症例に関する精神分析的考察(シュレーバー)フロイト全集11、岩波書店 2)「自伝的に記述されたパラノイア(妄想性痴呆)の一症例に関する精神分析的考察」-「シュレーバー症例」、現代フロイト読本1、みすず書房 3)分裂的機制についての覚書、メラニー・クライン著作集4、誠信書房
臨床心理士 上智大学
講義テーマ「自我心理学の意義を再考する」
二者心理学的観点が強調されるようになった今日の精神分析の流れの中で、自我心理学が重視している一者心理学的観点についてその意義を再検討し、精神分析状況の複雑さを浮き彫りにすることを試みます。
【参考文献】1)「精神分析の技法と実践」ラルフ・R・グリーンソン(著), 松木 邦裕(監修), 清野 百合(監訳) 2)「精神分析マインドの創造」フレッド・ブッシュ(著),妙木浩之(監訳), 鳥越淳一(訳)
Tavistock Clinic
講義テーマ「精神分析における治療者・患者関係」
精神分析の臨床を考えていく中で、分析家と患者の関係性を考えていくことは、不可欠なことです。ただ、どのように考え、理解するのかは、複雑であり、多岐にわたる要素が存在します。このセミナーが、その果てのない世界の理解の一歩のきっかけとなればと思います。
紙屋町こころのクリニック
講義テーマ「ウルフマン – パーソナリティ病理と倒錯」
ウルフマンとして知られるこの症例報告においてフロイトは、成人の神経症が幼児神経症を基礎にしていることを実証しようと試みました。
患者の連想にはフロイトへの転移も豊かに表現されています。
白百合女子大学大学院/こども・思春期メンタルクリニック
講義テーマ「ハンス – エディプス、外傷と同胞葛藤」
ハンスの症例は、フロイトがエディプスの実証として論じたものです。これに加えて、外傷、同胞葛藤と視点から概観するとより立体的にハンスを理解することができ、さらにハンス家の背景も含めて考察します。
小林メンタルクリニック
講義テーマ「ヒステリー研究 – 精神分析を生み出した患者たち」
2025年に惜しくも亡くなったブリトンは、アンナ・Oなどを詳細に研究し、ヒステリー者のパーソナリティを、原光景からの疎外体験を受け入れることができない病理としてとらえました。フロイトとの交流を通して精神分析を生み出したヒステリー者とは誰なのかを、現代的な光から照らし出しましょう。
浅田心療クリニック
講義テーマ「ラットマン – 強迫症と書かれなかった母子関係」
ねずみ男は重度の強迫症状でさえヒステリー症例で試みたのと同じ技法で父親転移を扱い治療可能であることを論文では証明した。ところが実際の面接記録で前景化する母親転移と母親への同一化が全く扱われていない。この問題について考えてみたい。
【参考文献】1)フロイト,S. (1909). 強迫神経症の一例についての見解(症例「鼠男」).岩波書店(10),2008 2)衣笠隆幸.(2005).転移―愛と憎しみの精神分析.現代のエスプリ第442号 3)Mahony, P. J. (1986). Freud and the Rat Man. Yale University Press.
大阪経済大学大学院
講義テーマ「子どもの心理療法のアセスメント」
子どもの安定的な心理療法を維持するためには、開始前の丁寧なアセスメントが欠かせません。児童養護施設や教育相談など、様々な設定の中で、実際にどのようにアセスメントを行うのか、検討します。
【参考文献】1)「子どもと青年の精神分析的心理療法のアセスメント」(平井正三・脇谷順子編 誠信書房、2021年) 2)「子どもの精神分析的心理療法のアセスメントとコンサルテーション」(鵜飼奈津子監訳 誠信書房、2021年) 3)「セミナー 子どもの精神分析的心理療法」(木部則雄、平井正三編 岩崎学術出版社、2024年)
新大阪心理療法オフィス
講義テーマ「精神分析的心理療法のアセスメント総論」
心理療法やその他の支援に際しておこなう、精神分析的な理解の枠組みを用いたアセスメントについて、限界などにも注目しつつ皆で考えてみましょう。ばらばらに散らばった困難の有り様を集めて再構築するアセスメントは、患者や治療チームを支えようとする試みの一部です。
【参考文献】1)仙道由香, 2019/2025, 心理療法に先立つアセスメントコンサルテーション入門, 誠信書房. 2)Evans, M. 2016, The role of psychoanalytic assessment in the management and care of a psychotic patient, in Makin Room for Madness in Mental Health: The Psychoanalytic Understanding of Psychotic Communications, Routledge.(エヴァンス[著], 仙道由香[訳], 2022, 精神病的な患者の管理およびケアにおける精神分析的アセスメントの役割, in チーム医療の現場を支える精神分析的アプローチ, p.121-134, 誠信書房.)
沿 革

関西精神療法研究会(KSK)の立ち上げ
小林和(精療クリニック小林院長)が関西初の精神分析セミナーである「関西精神療法研究会KSK」を立ち上げた。第1回講師は西園昌久、第2回は小此木啓吾であり、関西地区における精神分析のリーダーを輩出する母体となった。

精神分析研究会・神戸 発足
神戸大学の木曜会とKSKが合併し、小林俊三(当時は神戸大学)を代表として、「精神分析研究会・神戸」が発足した。

小林俊三が研究会代表に就任
分析協会の訓練のために代表を離れていた小林俊三が代表に復帰した。

研究会の基本方針を巡ってこれまでの運営委員が離れ、新たに複数の運営委員を迎えた。対象関係論を中心に諸学派の基礎を提供していくこと、精神分析のトレーニングを十分に受けた人物を講師に招くことを方針とすることが再確認された。
運営委員:
小林俊三(代表)
飯塚暁子
小畔美弥子
越道理恵
齊藤幸子
松村博史




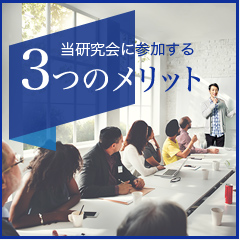
講義テーマ「ドラ – ヒステリーを現代的に解釈する」
フロイトはドラ症例での治療失敗体験から「転移」を発見しました。今回、改めてヒステリーとは何か、転移とは何か、そもそも精神分析によってヒステリー治療は可能なのか、そうした根本的な問いを探求し、臨床理論を知る機会を提供いたします。